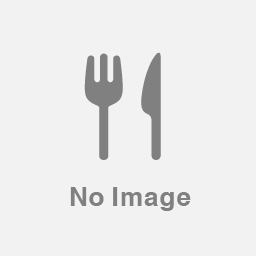『光る君へ』が絶好調に面白くて段田さんがすごいいいものだからやっぱり見てみたい!ってことで『リア王』チケット取っちゃいました。いやー見に行ってよかったね!
シェイクスピア見るのはジョン王に続いて2回目。前回は予習なしで挑んだものの、シェイクスピアはセリフ回しも独特だしやっぱり予習あった方がよかったなあと感じたので今回はちゃんと読んでから見に行くことにしました。
うん、読んでからにして正解でしたね。話の筋や関係性を頭に入れてから見ることができたので入りやすかったです。以下、ネタバレに触れてます。
しかしあれですね、本読んだ時もだが観劇しても地獄絵図がすごくてですね。クライマックスの地獄感がすごい。悲劇というより地獄絵図なんだよね。やだー何この地獄…みたいな。イヤミスとか全然平気な人なんだけどきつい…って思う程にしんどいですな。直球勝負で老害を描いていてその報いも受けるわけだけど何もそこまで奪わなくてもって思っちゃうのは私がそれだけ年を重ねたからかもしれません。自業自得とはいえ、あまりに残酷だなあと思ってしまう。愚かな王への罰を回避するポイントはいくつもあったがそれに気づかなかったから仕方ないんだろうけど。先日退場した兼家の晩年と重なる部分があって段田さんの演技にぞわっとした。
『光る君へ』からはもう1人、玉置玲央も出ている。私としては『ジョン王』以来。玉置玲央の声って通りがよくてすごく舞台映えするよねえ。こちらもまた、『光る君へ』と微妙に役が被ってるという。人を欺き陥れ、ありのままの自分では父からの愛は得られず自滅していく男ってねえ。予習しながら楽しみにしていたのでホクホクでした。
徹平くんはパンイチになったり逆立ち歩きをしたりと体張ってましたね。予習した時にトムの時のエドガーをどう演出するのかと思ったらそうきたのかーと。徹平くん38歳ってマジか…全然見えないよ。
舞台は中世ヨーロッパだけど衣装はスーツやパーカーだったりと現代風でセットもシンプル。白い壁はスクリーンとしての役割を担わせたりマジックで文字を書いたりも。演出の意図としては『リア王』という作品を通して現代の高齢化社会を照らすみたいな狙いなのかなあ。
リーガンが登場時は姉妹おそろいのピンクのパンプスなのに早々に舞台上で靴を脱ぎ、再登場時には白いスニーカーに履き替えていたのはどういう意図があるのだろうか。靴トラブル?と最初は思ったのだが検索すると他の回でも同じことをしていたそうなので演出の一環なんでしょうね。3姉妹おそろいでいるのをやめて自分に合う靴で自分らしくいくと反旗を翻すリーガンの思いの表れとかなのかなあ。よくわかんないや。
白い壁は途中で上がり、舞台の奥行きが倍になる。ラスト、再び白い壁が降りてきてその手前にはケント、エドガー、オールバニーが立っている。つまりこれって白い壁によって閉ざされたところは死者の世界ってことなんだよね。死者と別れて生き残った者たちはなすべきことをするのだ。
玉置玲央が観客にスマホの電源切ってないことに対してXで苦言を呈してるんだがこれ本当に恥ずかしい。演者にこんなこと言わせないで欲しい。何度も何度も繰り返し劇場でアナウンスされていたにもかかわらずLINEらしき着信音はなるのは本当にあかんと思う。色んな方向からせき込む音が聞こえてきたり「ぶほほほほん」「ごふふふふん」って大きな音で鼻鳴らす音がずっとしてたのも嫌だった。5分に1回くらいでは鼻鳴らしてたもん。
入り口横にあった上白石萌歌ちゃんのスタンド花。少しだけ萌歌ちゃんが歌う場面があるんだけど、透明感のある歌声が聞けて良かった。